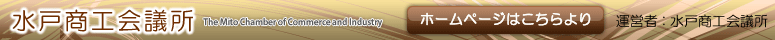元山町にある神應寺は、佐竹義宣(さたけよしのぶ)の招きを受けた三十二代遊行上人(ゆぎょうしょうにん)普光(ふこう)が、天正十九年(1591)、藤沢小路(ふじさわこうじ)神生平(現在の梅香二丁目)に堂宇(どうう)を建立したのが基で、当初は藤沢道場と称し、藤沢山清浄光寺(とうたくさんしょうじょうこうじ)(神奈川県藤沢市)の復興まで、ここが時宗(じしゅう)の本拠となった由緒ある寺です。寛永十(1633)年に神應寺と改称し延宝八(1680)年、現在地に移されました。
元山町にある神應寺は、佐竹義宣(さたけよしのぶ)の招きを受けた三十二代遊行上人(ゆぎょうしょうにん)普光(ふこう)が、天正十九年(1591)、藤沢小路(ふじさわこうじ)神生平(現在の梅香二丁目)に堂宇(どうう)を建立したのが基で、当初は藤沢道場と称し、藤沢山清浄光寺(とうたくさんしょうじょうこうじ)(神奈川県藤沢市)の復興まで、ここが時宗(じしゅう)の本拠となった由緒ある寺です。寛永十(1633)年に神應寺と改称し延宝八(1680)年、現在地に移されました。この寺には、江戸時代の作と考えられる木造の観音像(像高約13)を安置していますが、この観音像は、蹴鞠(けまり)をしているかのように左足先を少し上げた珍しい形をしており、雷を蹴り上げて信者を救ったという伝説を伴うもので、「蹴上げ観音」と呼ばれています。
また、当寺には、居合い術田宮流中興の祖といわれる和田平助正勝(わだへいすけまさかつ)や、いわゆる天狗党として西上し、最後には敦賀で切られた軍学者山国兵部(やまぐにひょうぶ)共昌の墓、同じく敦賀で殉職した田丸稻之衛門(たまるいなのえもん)直允(山国兵部の実弟)家の墓所などがあります。
 和田平助は威公・義公時代の水戸藩士で、食録三百石。居合い術で高名ですが、「馬養論」という著述もあると伝えられています。天和3年(1683)、派閥の争いに巻き込まれて暇を賜わった折、水戸を去るにあたって暴言を吐いたとして罪に問われ、今の加倉井の中根寺(ちゅうこんじ)のあたりで自害しました。
和田平助は威公・義公時代の水戸藩士で、食録三百石。居合い術で高名ですが、「馬養論」という著述もあると伝えられています。天和3年(1683)、派閥の争いに巻き込まれて暇を賜わった折、水戸を去るにあたって暴言を吐いたとして罪に問われ、今の加倉井の中根寺(ちゅうこんじ)のあたりで自害しました。