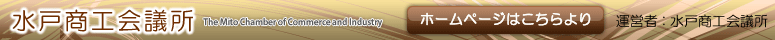明治29年東京美術学校助教授となり、大観の雅号を用いるようになります。同31年の学校騒動では校長岡倉天心の後を追って辞職し、日本美術院の創立に力を尽くしました。このころ試みた没骨画法(もっこつがほう)(無線描法)は、伝統的な線描を省略したために朦朧体(もうろうたい)と酷評されました。天心は明治39年再興美術院を五浦に移しましたが、ここでも大観は下村観山、菱田春草、木村武山らと天心の目指した日本画革新のために努力を続けました。

昭和6年には帝室技芸員に任命され、昭和12年第一回の文化勲章を受章しました。
代表作「生々流転(せいせいるてん)」は重要文化財に指定され、「流燈(りゅうとう)」「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」など数多くの名作を残しました。昭和33年東京で亡くなりました。墓は東京の谷中墓地にあります。