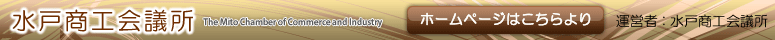水戸藩初代の藩主頼房(よりふさ)公(威公)は、愛妾谷久子(ひさこ)の懐胎を知ると、なぜか、家老の三木之次(みきゆきつぐ)に堕胎を命じましたが、三木夫妻は、ひそかに自宅で分娩させました。無事出産したのが後の光圀公です。胞衣(えな)はこの邸の隅に埋められ、塚の上に小さな石の碑が建てられました。胞衣を、特別に作った桶や壷に入れて恵方(えほう)(その年の開運の方角)に埋めることは、古代からある習俗です。この胞衣塚(えなづか)は、敷地の整備に伴って、常陸太田の西山荘に移されました。
光圀公は五歳で認知されて水戸の城に入るまで、ここで三木の子として育てられ、六歳で正式に世子として江戸の藩邸に迎えられました。
その後、この邸は柵町御殿(さくまちごてん)とか柵町の亭などと呼ばれました。隠居後の光圀公が訪れたある年などには、三木の一族も集まって酒宴が開かれましたが、そのときの光圀公の歌が『常山詠草(じょうざんえいそう)』に載っています。
朽残る 老木の梅も 此宿のはるに二たひ あふそ嬉しき
ちなみに、この梅の木は、光圀公の母久子が、手ずから植えた実生の梅です。